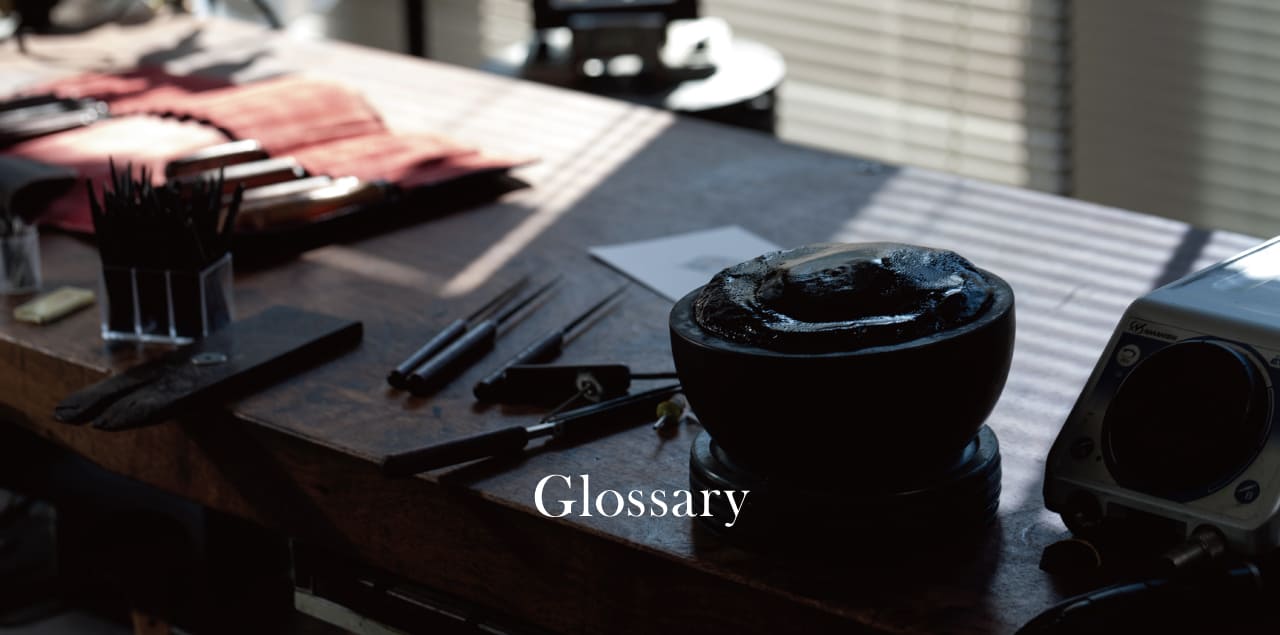象嵌
象嵌(ぞうがん)は、金属の表面に溝を彫り、そこに異なる金属や素材をはめ込む伝統的な工芸技法です。日本には古墳時代に伝わり、江戸時代に大きく発展しました。刀の装飾や武具、工芸品に使われ、繊細で美しい模様を生み出します。象嵌には技法に種類があり、それぞれの技法で異なる表現が可能です。現在では、ジュエリーや工芸作品に引き継がれています。
高肉象嵌
高肉象嵌(たかにくぞうがん)は、金属の表面に模様を浮き彫りのように立体的に仕上げる技法です。まず金属に溝を彫り、そこに別の金属をはめ込みます。はめ込んだ金属が、素地よりも高く盛り上がるのが特徴です。最後に表面を彫刻し、さらに立体感を出します。刀の飾りや工芸品に使われ、特に花や動物の模様をリアルに表現するのに適しています。
平象嵌
平象嵌(ひらぞうがん)は、金属の表面にくぼみを作り、そこに別の金属をはめ込んで模様を作る技法です。嵌め込む金属は、彫った深さよりもやや厚く切り出し、余分な高さを削り取ります。様々な技法があり、中国漢時代の盤や筒、鏡などに見られます。
薄肉彫
薄肉彫(うすにくぼり)は、模様を薄く浮き彫りのように表現する方法です。絵画と彫刻の中間のような技法で、作品に繊細な立体感を生み出します。西洋の深い彫刻とは異なり、表面に水が盛り上がったような滑らかな質感を作るのが特徴です。制作には特別な鏨(たがね)を使い、丁寧に彫り、研ぎ、磨きを重ねて仕上げます。
肉合彫り
肉合彫り(ししあいぼり)は、江戸時代に生まれた金属工芸の技法です。金属の表面を削り、模様を周囲からくり抜くことで、浮き彫りのような立体感を作り出します。まるで薄い彫刻が沈み込んでいるように見えるのが特徴です。
ロウ流し象嵌
ロウ流し象嵌(ろうながしぞうがん)は、日本の伝統的な金属工芸技法の一つで、金属の表面に溝や模様を彫り込み、そこに溶かした金属を流し込んで装飾を施す技法です。この技法は、模様が滑らかに埋め込まれた美しいデザインが特徴です。
NC彫刻
NC(Numerical Control)彫刻は、コンピューター制御によって精密な彫刻を施す技術です。CADデータをもとにNC工作機械が工具を動かし、金属や木材などの素材に彫刻を行います。手作業では難しい細かな模様や立体的なデザインも、高精度かつ均一に仕上げることが可能です。本プロジェクトでは、象嵌の下彫りに活用され、伝統技法と組み合わせて活用しています。
レーザー彫刻
レーザー加工は、高エネルギーのレーザービームを照射して金属や樹脂、木材などの素材を切断、彫刻、溶接する技術です。微細加工が可能で、デザインデータをもとに高精度な彫刻や切断を行います。本プロジェクトでは、象嵌の下彫りや細密な模様の刻印に活用され、伝統技法と組み合わせて活用しています。